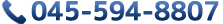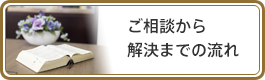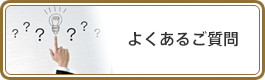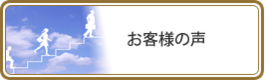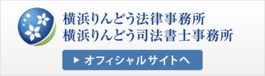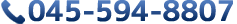寄与分を主張して遺産分割をまとめた事例
事 例
主な遺産は、戸建て不動産(土地・建物)で、長年、介護が必要だった母が亡くなりました。
長女は、母と同居をして、介護に尽力していました。
もう一人の相続人である長男は、別に住んでおり、介護には何も協力をしていませんでした。
この遺産分割において、長女側から、長男に対して、寄与分を主張したいということで、依頼を受けました。
長女は、母と同居をして、介護に尽力していました。
もう一人の相続人である長男は、別に住んでおり、介護には何も協力をしていませんでした。
この遺産分割において、長女側から、長男に対して、寄与分を主張したいということで、依頼を受けました。
示談交渉での解決
ご依頼をいただいた後、「寄与分」の主張を支える様々な証拠の収集を開始しました。
相当程度の資料が集まり、仮に、遺産分割調停+寄与分調停となった場合でも、これであれば、寄与分の主張が認められる可能性が十分にあると考え、相手方へ、寄与分を加味した内容での遺産分割協議を提案しました。
紆余曲折はありましたが、相手方も、長女の介護の苦労は理解しているようで、最終的に、寄与分を考慮した内容で、遺産分割協議がまとまりました。
相当程度の資料が集まり、仮に、遺産分割調停+寄与分調停となった場合でも、これであれば、寄与分の主張が認められる可能性が十分にあると考え、相手方へ、寄与分を加味した内容での遺産分割協議を提案しました。
紆余曲折はありましたが、相手方も、長女の介護の苦労は理解しているようで、最終的に、寄与分を考慮した内容で、遺産分割協議がまとまりました。
弁護士コメント
相続人中に、被相続人(亡くなった方のこと)の療養看護などに特別に尽力した方がいる場合には、「寄与分」を主張することがあります。
この寄与分が認められると、その特別な尽力の分が金銭に換算され、法定相続分より多くの遺産を取得することができます。
しかしながら、この「寄与分」の主張というのは、裁判所で認められるハードルはとても高く、相当の尽力をしている必要があります。
(弁護士コラム「療養看護型の「寄与分」(キヨブン)の実例」ご参照)
本件は、依頼者の方の話を聞くと、次のような事情がわかり、これであれば「寄与分」の主張が裁判所の審理においても認められると感じた事例になります。
〇 依頼者(長女)は、約11年間、同居して母の介護に携わっている
〇 被相続人(母)の要介護度の状況は、同居開始時には「要介護3」、亡くなる7年前からは「要介護5」※ほぼ寝たきりの状態
〇 長女は、介護に専念するために、最後の6年間は、仕事を辞めて、無償の介護を続けた
〇 概ね週2回程度のデイサービス、概ね週2回程度の訪問介護の援助は利用していたが、それ以外は、ほぼ付き切りで自宅で療養看護した。
〇 介護・看護の状況も、行動・移動全般の介助、排泄物の世話、食事の介助、入浴介助、口腔ケアなどを一人で行っていた
〇 介護期間中には、長女自身が腰椎圧迫骨折+脊柱管狭窄症(母を持ち上げる等のしていたため)と診断され、自身の心身に支障をきたす中でも介護を続けた
以上のような状況でしたので、弁護士としても、これであれば、何も介護に尽くしていない長男と同じ法定相続分ということはおかしいであろうと考えて、寄与分を前提にした遺産分割を主張していきました。
本件では、最終的に調停手続きになることなく、遺産分割協議がまとまったのですが、調停・審判に備えて、徹底的な資料収集も行いました(審判になれば、証拠が非常に重要です)。
収集した資料は、概ね次のようなものになります。
・医療カルテ 全て
・デイサービス、訪問看護の利用記録 全て
・依頼者が辞めた仕事の給与明細など
・依頼者の腰の圧迫骨折の診断書+当時のカルテ
・介護認定記録 全て
・被相続人(母)の写真
・例えば、オムツの購入履歴がわかる資料(カード利用明細や、レシートなど)
寄与分の主張は、かなりハードルが高いものであり、裁判所の審判では容易には認められないものと考えていますが、それでも、もちろん相当の尽力をしており、それを主張したいというお考えがある場合には、寄与分を主張していくべきと考えています(ただし、資料収集だけでも大変な作業になりますので、依頼者の方もある程度、覚悟を持って臨んでいただく必要があります。)。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
この寄与分が認められると、その特別な尽力の分が金銭に換算され、法定相続分より多くの遺産を取得することができます。
しかしながら、この「寄与分」の主張というのは、裁判所で認められるハードルはとても高く、相当の尽力をしている必要があります。
(弁護士コラム「療養看護型の「寄与分」(キヨブン)の実例」ご参照)
本件は、依頼者の方の話を聞くと、次のような事情がわかり、これであれば「寄与分」の主張が裁判所の審理においても認められると感じた事例になります。
〇 依頼者(長女)は、約11年間、同居して母の介護に携わっている
〇 被相続人(母)の要介護度の状況は、同居開始時には「要介護3」、亡くなる7年前からは「要介護5」※ほぼ寝たきりの状態
〇 長女は、介護に専念するために、最後の6年間は、仕事を辞めて、無償の介護を続けた
〇 概ね週2回程度のデイサービス、概ね週2回程度の訪問介護の援助は利用していたが、それ以外は、ほぼ付き切りで自宅で療養看護した。
〇 介護・看護の状況も、行動・移動全般の介助、排泄物の世話、食事の介助、入浴介助、口腔ケアなどを一人で行っていた
〇 介護期間中には、長女自身が腰椎圧迫骨折+脊柱管狭窄症(母を持ち上げる等のしていたため)と診断され、自身の心身に支障をきたす中でも介護を続けた
以上のような状況でしたので、弁護士としても、これであれば、何も介護に尽くしていない長男と同じ法定相続分ということはおかしいであろうと考えて、寄与分を前提にした遺産分割を主張していきました。
本件では、最終的に調停手続きになることなく、遺産分割協議がまとまったのですが、調停・審判に備えて、徹底的な資料収集も行いました(審判になれば、証拠が非常に重要です)。
収集した資料は、概ね次のようなものになります。
・医療カルテ 全て
・デイサービス、訪問看護の利用記録 全て
・依頼者が辞めた仕事の給与明細など
・依頼者の腰の圧迫骨折の診断書+当時のカルテ
・介護認定記録 全て
・被相続人(母)の写真
・例えば、オムツの購入履歴がわかる資料(カード利用明細や、レシートなど)
寄与分の主張は、かなりハードルが高いものであり、裁判所の審判では容易には認められないものと考えていますが、それでも、もちろん相当の尽力をしており、それを主張したいというお考えがある場合には、寄与分を主張していくべきと考えています(ただし、資料収集だけでも大変な作業になりますので、依頼者の方もある程度、覚悟を持って臨んでいただく必要があります。)。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。